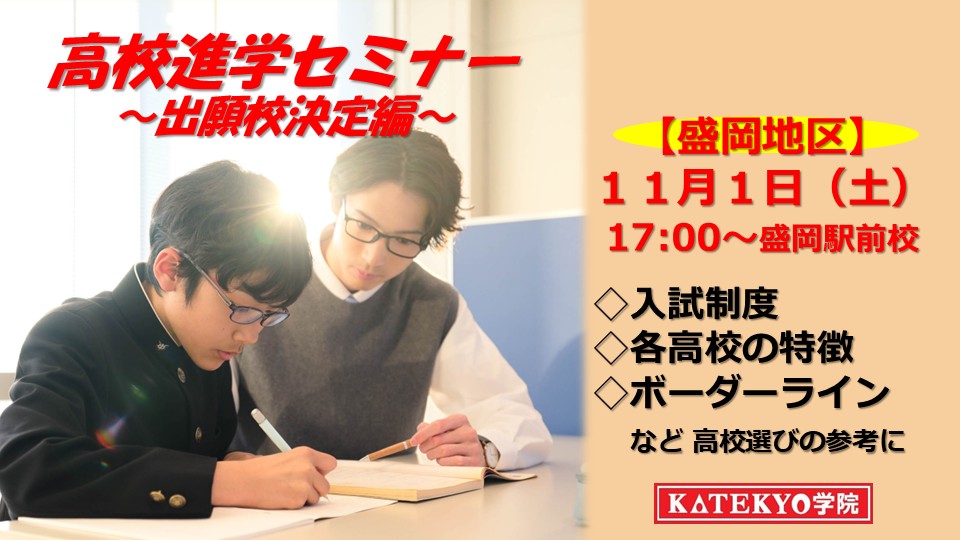お盆はなぜ13日〜16日?その理由、カレンダーにあり!
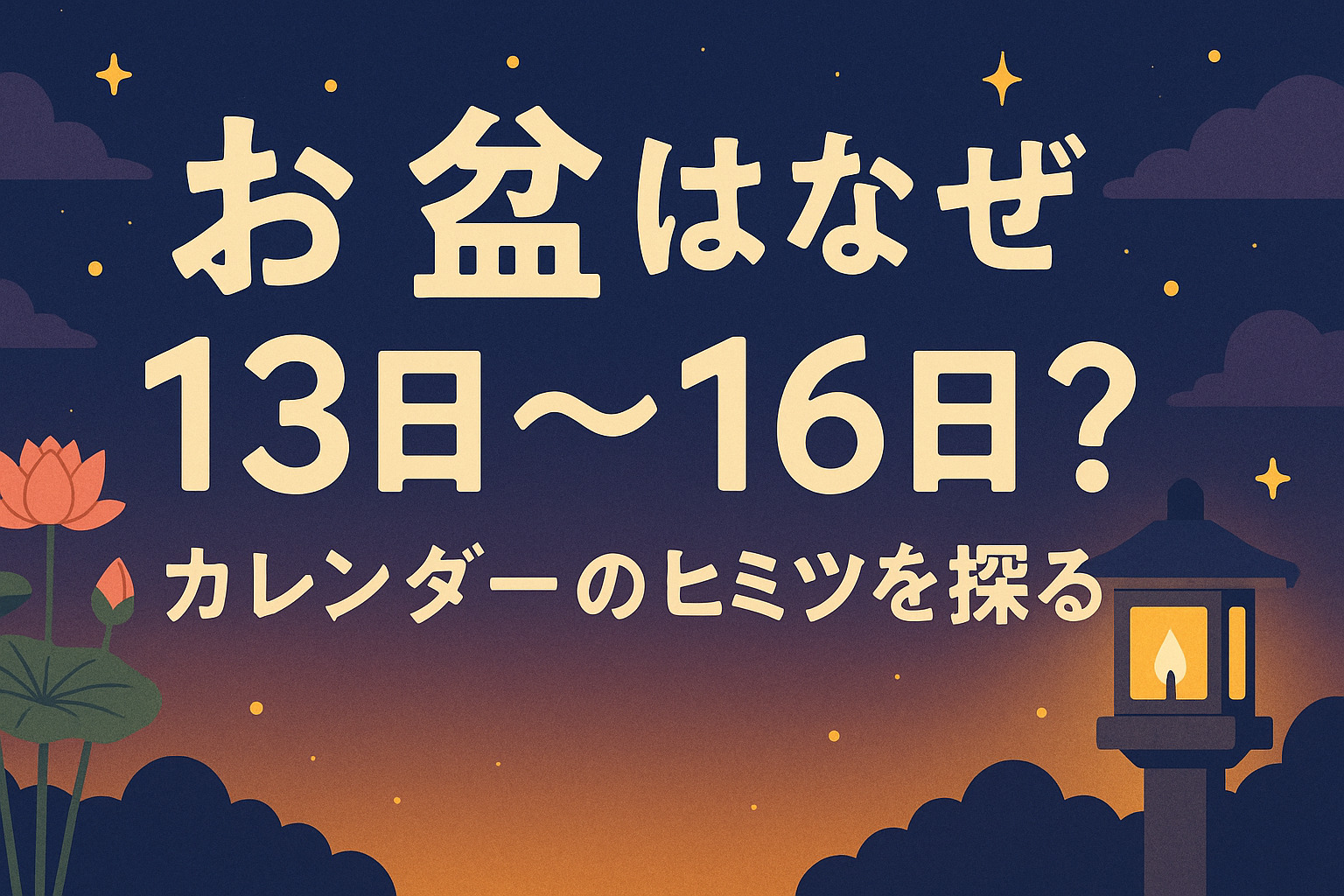
「お盆って、毎年だいたい8月13日〜16日だよね?でも、なぜその日なの?」
実はこの日付、昔の“旧暦”と関係があります。
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といって、ご先祖さまの霊を迎えて供養する行事です。もともとは旧暦の7月15日ごろに行われていましたが、明治時代にカレンダーが太陽暦(今の暦)に変わったことで、旧暦7月15日=今の8月15日あたりに移動したのです。そのため、8月13日を迎え火、16日を送り火として、「お盆」はこの時期に定着したわけですね。
ただし、地域によっては今でも旧暦ベースで7月に行っているところもあるんですよ。
こうしてカレンダーと文化のズレが生まれるのも、歴史を学ぶヒントのひとつ。普段使っている「日付」にも、意外と奥深い秘密があるんです!